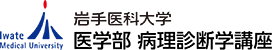診療
附属病院の病理診断業務全般を行っています。業務の内容としては生検診断、外科材料の組織診断、細胞診断、術中迅速診断および病理解剖です。附属病院はその性格上多数の検体が提出されますが、その組織診件数は年間約1万1千件と東北地区においてhigh volume centerとなっております。加えて関連病院の病理診断支援を行っており、それらを加えますと年間2万件超の組織診断数となります。さらには複数の病院間とネットワークを結んで遠隔迅速病理診断を行い、地域医療にも大きく貢献しております。また最近は遺伝子パネル検査が日常の臨床でルーチンに行われるようになってきていますが、これらの検査には主に病理組織検体が用いられるため、それらの検体の確認を行っています。
病理診断はその結果そのものが多くは最終診断となるため非常に重要であり、患者さんの予後を予測したり治療方針を決定する際のメルクマールとなりえます。そのため、なるべく早く精度の高い病理診断を臨床に伝えることが、我々の任務と考えています。また、臨床側の要求を満足する病理診断を下すために、われわれは臨床側とカンファレンスを定期的に開いています。
「臨床に役立つ病理学」が臨床病理部門の基本理念です。病理診断は臨床に役立ってこそ、その意味があると考えます。
教育
病理学の講義は現在では、3M器官病理学(講義、実習)と4M臨床病理学(講義)を担当しています。器官病理学では病理学各論として臓器別に学習を行い、引き続きバーチャルスライドを用いて実習を行っております。総論で学んだ各種異常についての意義を各個別の疾病について学ぶことを目的としております。4M臨床病理学では日常行われている病理診断の手順について、症例を提示しながら講義を進めていきます。実際のところ、病理診断は形態診断のみではなく、臨床的背景、各種検査所見、肉眼所見を統合して最終診断が下されています。この講義により実際の診療における病理診断の重要性を理解させることを目的としております。
臨床実習では座学で学んだ知識を元に、実臨床における病理診断学の役割について実際に実習を行い学んでもらいます。具体的には病理標本の作製、手術材料の切り出し、組織診断(生検、手術検体)、細胞診断、などを行ってもらい各臨床科との関わりを認識してもらいます。また病理解剖症例の症例を用いてCPC形式の実習を行っています。最終日にはプレゼンテーションを行い臨床病理相関についてまとめてもらいます。
卒後教育として岩手県内の研修医CPCの多くを担当しています。附属病院はもちろんのこと、胆沢病院、中部病院、久慈病院、二戸病院、盛岡市立病院、北上済生会病院の研修医らが1週間当講座にきてCPCのプレゼンテーションを解剖医の指導の元で作成しております。近年新型肺炎の影響により病理解剖数が減っており、担当症例に苦慮しております。病理解剖はその病院の質を表すといわれます。臨床の先生方におかれましてはお忙しいと思われますが、ご協力をお願いいたします。
研究
腫瘍学(Oncology)を基本にした研究を行っています。各種腫瘍、特に癌の生物学的特徴を明らかにすべく切除された材料を用いて、免疫組織化学や遺伝子異常、遺伝子発現解析を行っております。そして、これらの結果と病理診断を含む臨床病理学的背景との関係性についても検討し、臨床に還元しています。
現在行っている主な研究は以下のようになります。
1) 原発性肺腺癌組織亜型間の分子病理学的差異についての検討
2) 硬化性歯原性癌についての臨床病理学的および分子病理学的検討
3) メルケル細胞癌の腫瘍微小環境状態についての検討
4) FFPEブロックの質的状態のついての検討
5) 切除検体及び生検の病理組織に基づくdMMR/MSI型胃癌の同定
6) 稀少肺癌の臨床病理学的および分子病理学的研究
7) 大腸癌におけるTP53遺伝子変異解析の免疫組織化学的解析による代替可能性の検討
8) 虫垂鋸歯状病変における臨床病理学的および分子病理学的研究